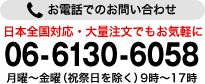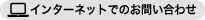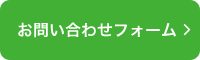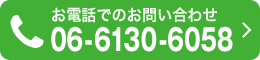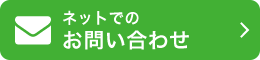スペシャルインタビュー
- グリコノベルティサイト
- スペシャルインタビュー
- 株式会社浅野製版所様に訊く、健康経営推進のポイント!
株式会社浅野製版所様に訊く、健康経営推進のポイント!
株式会社浅野製版所様は、東京・築地で80年以上の歴史をもつ広告・印刷のプロフェッショナル企業です。健康経営優良法人(中小規模法人部門)は2017年の初回から、さらに2021年からはブライト500に連続で認定されるなど、健康経営の取り組みで高い注目を集めています。 今回、取り組みを推進している健康経営推進チームの新佐絵吏さん(事業開発部部長/産業カウンセラー・健康経営エキスパートアドバイザー)に、企業にとっての健康経営の意義やメリット、取り組み方などをお伺いしました。
(2025年 5月取材)

主な内容
(1)組織づくりとしての「健康経営」

――そもそも健康経営とは、どのような取り組みなのでしょうか?
経済産業省は健康経営を「従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資である」と位置付け、「健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義しています。少子高齢化が進む中、国の施策でも重視されており、「日本再興戦略」や「未来投資戦略」にも「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。
企業には経営的視点から従業員の健康を考え、その取り組みを実践することで事業の継続性を高めていくことが求められています。
健康経営の目的は「従業員を健康にすること」と考える方も多いと思いますが、私は「従業員が健康で働き続けられる組織をつくること」であると考えています。健康経営の推進というと、「禁煙の推奨」や「健康診断の受診義務化」など、指導的な側面が強調されがちですが、「どうすれば社員たちが元気に無理なく長く働けるか」を組織としてしっかり考え、仕組み化していくことが重要で、それが本来の健康経営につながっていきます。
現在、労働人口の減少は多くの企業にとって深刻な課題となっています。特に中小企業では、その影響が大きく、社員が一人抜けるだけで業務が回らなくなることも珍しくありません。これまでは「仕事だけに注力できる男性」が労働力の中心でしたが、今は育児中の女性や定年後のシニア層など、さまざまな人が働き手になっています。また、男性も育児や介護・地域活動など、仕事以外の役割を持つようになってきています。以前のように「仕事だけに注力できる人」は今後ますます減っていくと考えられますので、企業側は、どんな状況の従業員でも無理なく働ける方法を設計し、長く働いてもらえる体制を整えていくことが求められるでしょう。
(2)中小企業の経営を支える、健康経営のメリット
――健康経営に取り組むことで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず挙げられるのは採用活動への好影響です。最近では大学のキャリアセンターで「ホワイト企業の探し方」を学生に紹介するなど、若い世代の企業選びがより厳しくなっています。健康経営の認定を取得している企業は「働きやすい会社」として評価される傾向にあり、今後は「認定を取っていない=ブラック企業では?」と見られる可能性も出てきています。

また、健康経営を推進することでリファラル採用(社員や取引先など信頼できる人から紹介されて採用すること)やアルムナイ採用(一度退職した社員を再雇用すること)など、従来とは異なる採用手法も活用しやすくなります。 加えて、既存社員のエンゲージメントを向上させることも大きなメリットの一つです。多くの社員が仕事だけに注力できない状況が増えるなか、中小企業は限られた人的資本をいかに活用するかが問われています。健康経営の指標には組織の土台づくりや風土の見直しも含まれていますので、取り組みを進めることで働きやすい環境が整い、会社の安定にもつながります。
まとめると、健康経営は採用・定着・エンゲージメント向上のすべてにかかわり、会社の安定性や社会的信頼の向上にも寄与する、今の時代に不可欠な取り組みです。企業が事業を継続していくうえで、健康経営の推進はより重要性を増していくと考えられます。
(3)まずは「自社の健康課題」を見つけよう
――健康経営を始めるには、どこから手をつければいいのでしょうか?
最初の一歩って、やっぱり難しいですよね。健康になることを目的とすると、健康でない人を排除するという組織風土を作ってしまうという危険性があります。加えて、人の健康にかかわることなので、個人情報の取り扱いは細心の注意が必要です。さらに経営層が「健康は個人の問題」と理解してくれなかったり、社員が「自分の健康状態について会社に介入してほしくない」と協力してもらえなかったりと、組織の中で温度差が生じやすいのも事実です。結局、思うような成果が出ことも少なくありません。 だからこそ、最初からすべてをやろうとせず、「どのような健康課題があるのか」を見極め、スモールスタートで進めることが大切です。
多くの企業に共通する課題としては、「プレゼンティーイズム」の問題が挙げられます。プレゼンティーイズムとは出勤しているものの体調不良で十分なパフォーマンスが発揮できないことを言います。例えば、長時間労働による疲労、花粉症などのアレルギー症状、肩こりや腰痛、メンタル不調など、さまざまな要因で「全力で働けない」などの状況です。これらをただの個人の症状として改善しないまま放っておくと、生産性の低下を引き起こすだけでなく、ミスや事故につながる可能性もあります。 また、業界特有のもの(例:IT業界=長時間のデスクワーク、建設業界=熱中症)や、職種特有のもの(例:自動車運転や倉庫作業=腰痛)などは、企業として避けて通れない、早急に改善すべき健康課題です。 当社(広告業)では当初、長時間労働が最大の健康課題であると考えていましたが、その根底には「社内のコミュニケーション不足」がありました。各々が忙しすぎて協力体制が築きにくい雰囲気があり、一人で仕事を抱え込んだ結果、疲弊し、離職者が増えるという悪循環が生じていたのです。 そこで、まずは業務の棚卸を行い、やらなくて良いことを洗い出しました。さらに社内制度やシステムを見直し、休みやすい環境の整備など「企業の土台づくり」に着手し、段階的に課題の解決を進めていきました。これらと同時に健康経営を推進することで、組織的なフォローやサポートが可能となり、企業が抱えるリスクの低減にもつながっていったように思います。

――コミュニケーションが取りやすい環境を整えるために、どのような対応をされたのでしょうか?
当社では健康経営推進の観点から、社内イベントや福利厚生に「健康」の要素を盛り込む工夫をしています。例えば社内イベント際には健康研修を併せて実施する、イベントの景品には必ず健康グッズを選ぶなど、機会があれば何でも健康につなげるようにしています。
社員から好評だった取り組みとしては、アルコール体質遺伝子検査とセットにした研修があります。酒造メーカーの研究員の方にオンラインで研修をしていただき、その後、希望者にアルコール体質遺伝子検査を実施しました。自身のアルコール体質のタイプを知ることで、病気のリスクや自分に合った飲み方を知ることができます。さらに社内でアルコール体質の型が描かれたステッカーを制作し、それを貼って懇親会を開催するなど、相手の健康に配慮しながらしっかりとコミュニケーションを取れる学びの機会を作っています。
そしてすでに社員に定着しているコミュニケーション施策のひとつにグリコ「健康ギフトセット」プレゼントがあります。最初に導入したのはコロナ禍の時期です。当時は新年会や歓迎会などが全くできず、社員の7割が在宅勤務だったため、なかなか顔を合わせる機会がありませんでした。そんな折、グリコさんから「健康ギフトセット」のご案内をいただきました。価格も手ごろで、ギフト感のあるパッケージ。中身はしっかり健康志向。企業として「社員の健康を気にかけていますよ」というメッセージが、自然な形で伝えられる点に魅力を感じました。「健康ギフトセット」なら、顔を合わせにくい状況でも「あなたの健康を大切に思っています」という気持ちをしっかり届けられます。
――「健康ギフトセット」のご活用ありがとうございます!社員の皆さんの反応はいかがでしたか?
とても好評です。家に持ち帰った社員からは、「子どもがとても喜んでくれた」という話も聞きました。社員の家族とつながりを持つ機会が少ないなか、当社の健康経営の取組みを認識してもらうきっかけにもなっていると思います。
コロナ禍のころは社員の自宅に直接郵送していましたが、現在では健康診断が終わった後に会社に立ち寄ってもらって配布するスタイルに変えて継続しています。健康診断に向けて頑張って摂生している社員もいます(笑)ので、そういった努力への労いとしてもぴったりだと感じています。
配布後の予備分は社内イベントの景品に使ったり、朝食の欠食対策として設置しているカプセルトイの景品にしたりと、いろんな場面でフル活用しています。
(4)社員の満足度92%。無理なく続ける健康経営のコツとは?
――浅野製版所では健康経営に向けて100を超える施策を講じておられるそうですね。社員の皆さんの反応はいかがですか?
少なくとも「当社が健康経営に力を入れている」ということは、社員にしっかり伝わっていると思います。取り組みの幅広さはもちろんですが、外部へ向けての発信や、社内のオンライン掲示板などを通じて、会社の姿勢をしっかりメッセージとして発信できている実感があります。
当社では定期的にプレゼンティーイズムや、ワークエンゲージメント、心理的安全性などのアンケートも行っていて、その結果を社員にも公表しています。その中には健康経営や働きやすさなどの満足度に関する項目も含まれていて、全体としての満足度は92%という非常に高い水準となっています。今後も社員の声に耳を傾けながら、よりよい職場環境づくりを進めていきたいと考えています。

――では最後に、これから健康経営を始めたいと考えている企業に向けて、アドバイスをいただけますでしょうか。
「よし、健康経営を始めよう!」と気合いを入れても、健康に精通した社員がほとんどいない中小企業であれば何から始めればよいかわからないのではないでしょうか。
でも、「企業の組織課題」として見ていくと、その中には必ず健康にかかわるテーマが含まれているはずです。
中小企業の健康経営の取組み事例が少ないため、業種や規模の違う他社を参考にしようとすると、「うちには無理かも」と感じてしまうかもしれません。しかし、大切なのは、社員が「何に困っているのか」「働き続けるうえで、どんな不安を抱えているのか」といったリアルな声を丁寧に拾うことです。そうすることで自然と、自社の健康課題も見えてきます。
「何をすればいいかわからない」と思ったら、まずは社員の声を聞いてみて、できそうなことから始めてみてください。そうすれば無理なく、長く続けていけるはずです。
そういう点では、グリコの「健康ギフトセット」は、最初の一歩にぴったりのアイテムだと思います。手軽で続けやすく、しっかりと気持ちが伝わる。これから健康経営に取り組もうと考えている企業にも、ぜひ一度試してみてほしいですね。(終)
取材・記事作成

夏野かおる
研究者をやりつつ株式会社(編集プロダクション)を経営。ICT教育、テクノロジー領域、ドローンが中心。最近ではAI(主にChatGPT)を活用した業務効率化も。農業用ドローンの資格保有。natsuno.kaoru@natsuno.biz